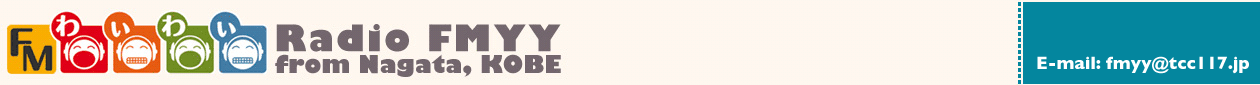今月の放送は、24回目を迎えた〈奄美ふゆ旅〉(2019.01.21-24)の報告を中心に番組を構成しました。
ゲストに、旅をともにした小説家の高木敏克さん。
①まず高木さんに旅の全体の印象を語ってもらいます。わたし(大橋)は今回沖縄経由で沖永良部島に入ったのですが、高木さんは鹿児島経由でした。20日(日)に小説家・中脇初枝さんの講演を聞くためです。今回の旅は文学紀行の様相を濃くしています。
②21日(月)最初に訪れた沖永良部島では、知名町公民館で、沖永良部島を舞台にした小説『神に守られた島』『神の島のこどもたち』(中脇初枝著)について、わたし、高木氏をふくめた四人で「読書会」を開催したことを報告。戦中、戦後(奄美の日本への復帰運動をふくむ)のエラブ社会の変動をよく記述しているその小説世界を、エラブの側から語り合ったのです。
③22日(火)つづいて訪れた徳之島では、島に住む俳人・亘余世夫さんに島を案内していただき、亀津で句会を開催したのです。俳句をつくるのは初めてという高木さんをふくめて、披講(作品を講評しあうこと)は島の文化を語ることにも言及され、愉しいひとときだったのです。
④23日(水)徳之島から奄美大島に向かう飛行機が故障で欠航となり、急遽、亀徳港から船に乗って奄美大島に向かいます。大島に到着した後、カトリック教会におもむき田端孝之神父に挨拶。その田端神父をまじえて、名瀬で地元新聞記者をまじえて、親睦会をもよおしたのです。
⑤24日(木)旅の最終日、飛行機便の都合で早く帰る高木氏を見送り、わたし詩人の仲川文子さんとランチタイム。奄美で詩について語ることの至福の時間を費やしたのです。
わたしの恒例の〈奄美ふゆ旅〉は人と会う旅です。今回も、一年ぶりに会う各島の友人・知人たちと、親しく語り合いました。しかし24年間の歳月は、島でであうひとの世代交代を実感するに十分なのです。去っていったひとたちの追憶と、追悼文をしたためる立場になってしまっています。
そして、この旅のことも南海日日新聞にまとめていますので、どうぞ読んでください。
★つむぎ随筆(南海日日新聞/2019年2月掲載)
◎語り部としての中脇小説
―大橋愛由等 詩人・出版社代表
ひととひとがつながり、多くの語りと抒情が交わされた。
今回で24回目となる〈奄美ふゆ紀行〉は、奄美の島々をめぐり、人と会い、語り、風土や人情を感受する旅なのである。そして、阪神・淡路大震災がおきた1・17の日に毎年仮死の状態となるわたしは、そこから甦る(黄泉帰る)ための再生に向かう通過儀礼の旅でもあるのだ。
最初に訪れた沖永良部島では、この島の戦中、戦後を舞台にした小説、中脇初枝著『神に守られた島』『神の島のこどもたち』をエラブの人たちと語り合う読書会を知名町公民館で催したのであった。
エラブを描いた小説は一色次郎、干刈あがたといったこの島の血を引く人間が表現した作品はあるが、数は多くない。久しぶりにエラブを舞台にした作品が登場したことになる。 小説といえども、この2書には戦中、戦後のエラブ社会の変動について書かれていることから史実(伝承的事実も含む)を正確に記述することが求められる。わたしが読む限りにおいて、正確に史実を踏まえて表現されていることを評価したい。
通奏低音のように鳴り響く沖縄への米艦船からの艦砲射撃、エラブへの米軍の空襲を逃げ惑いながらも生き抜き、いよいよ次はこの島に米軍が上陸する恐怖におののく毎日。そして島に不時着した特攻機に乗っていた日本兵との会話。
戦後になってからは、大山(知名町)のレーダー基地に駐屯していた米兵と、島民との間にほのぼのとした交流が交わされていた。奄美大島における米軍政府と復帰を希求するシマンチュとのとげとげしい関係とは異次元の世界だった。
この2書から見えてくるものは、〈語り部〉としての中脇作品の立ち位置である。研究書、歴史書では表出されにくい島の人たちの情念が小説という形でリアルに記述・再現され、エラブの歴史を再体験できるテキストとなりうるだろう。
この作家はもともと少年少女を描く巧みさがあり、この2書には何人かの少年少女たちの青春群像がよく表現され、成長物語としても読みうることから、この2書の続編として復帰後にヤマトへの交通や進学が容易になった島の青年たちの動向と情念が表現されるのかどうか注目していきたい。 (神戸市)