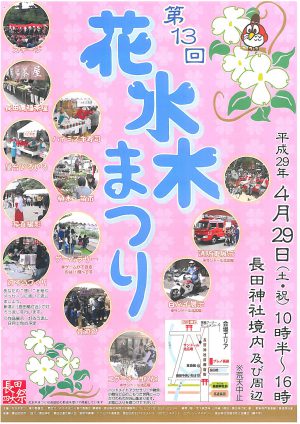FMわぃわぃは、1995年の阪神・淡路大震災を契機に多文化共生、メディア、災害とまちづくり、この3つを基本として活動を続けています。そして70年前に施行された日本国憲法の三原則(主権は人々にあり、その人々の基本的人権を尊重し保障し、そして戦争の放棄と武力の不保持を政府、国家に守らせるための立憲主義の根幹)にのっとった「まち」「社会」の構築をめざています。それには自分たち一人ひとりの生活に憲法というものがどのようにリンクしているのか、それぞれが理解する必要があります。
本日は災害という観点から基本的な法の順守、また法についての考えをわかりやすく読み解かれている室崎益輝氏の文章を、ご本人の了解を頂きましたので転載させていただきます。
◆災害救助法の改正に向けて(その1)・・特別基準の大切さ
5月3日は、憲法記念日である。70年前の昭和22年に、現在の憲法が施行されている。その憲法が施行された5か月後の10月に、災害救助法が施行されている。
災害救助法が70年も前に制定されたので、もはや時代遅れで陳腐化しており、全面的に改正すべきだという声が大きくなっている。災害救助法が今の被災者救援を妨げる元凶だという声さえもある。しかし、私はそうは思っていない。災害救助法が憲法や地方自治法と同時期に制定されたことをみても、そこには自治や人権擁護といったとても大切な考え方が貫かれている。それを、しっかり守らないといけないと思う。
無論、社会状況も前提とする災害の規模も制定当時とは大きく違ってきているので、その違いに配慮した修正がいるのは言うまでもない。ただ、その修正の声に押されて、大切なものまで修正してしまう「愚」は避けたい。変えるべきものと「変えてはならないもの」とを峻別して、災害救助法のあり方を論じなければならない。
変えてはならないものの一つは、災害の状況に応じて弾力的に法を運用するという考え方である。それは「特別基準」という救助法の枠組みに組み込まれている。今までの運用を見ると、この特別基準を活用して、40㎡(3K)の仮設をつくってきたし、寒冷地仕様の仮設もつくってきた。特別基準で、標準単価をはるかに超える700万円もする仮設住宅を認め、有珠噴火災害や中越水害など多くの災害で「借り上げ仮設住宅」を認めてきた。阪神・淡路大震災では、特別基準を使って希望者全員の仮設入居を可能にしている。
この3月末の内閣府の告示で、一般基準としての仮設の単価や規模の改正などがはかられたが、それらは上述したように特別基準ですでに実施してきたことで、その改正を諸手を挙げて高く評価することではない。より大切なのは、実態と必要に応じて弾力的に特別基準を適用することで、被災の状況に応じて支援をはかるという災害基準法の原点に立ち戻ることである。
◆災害救助法の改正に向けて(その2)・・災害保護と自立奨励
変えてならないものの一つに、災害救助法の基本目標とその根底にある基本理念がある。
災害救助法の第1条には、「災害にかかったものの保護をはかる」とあり、その制定時の国会の付帯決議には、「新憲法により保障されている国民の基本的人権及び財産権が侵害されることのないように」とある。
災害にかかったもの保護とは、災害によって自立あるいは自活できなくなった被災者に寄り添って、被災者が自らの力で立ち上がれるようになるまで救助し支援する責務が国にあることをいっている。被災者の人権を守り被災者に寄り添うことが求められている。
支援を必要とする被災者が存在する限り、被災者の要件を問わず、国籍や居住地を問わず、支援を必要としているすべての被災者に手を差し伸べることを災害救助法は求めている。被災者の実情に即して対処することを求めているのだ。それを「平等の原則」とか「災害保護の原則」と呼んでいる。
避難所に来た被災者と在宅している被災者、全壊の被災者と半壊の被災者を、応急支援の段階においては差別してはいけない。支援を必要としている人に必要な支援を与えるのが、救助法運用の基本原則である。この基本原則を忘れると、「避難所の被災者以外には救援物資を提供しない」といった誤った対応が生まれてしまう。
その一方で、災害救助法は「少しでも自立できる状況にある被災者」には厳しく自己解決を求めている。この自己解決要求を杓子定規にとらえると、特定の被災者しか支援をしないという「救貧主義」の罠にはまってしまう。
ところで、災害保護というのは「自立を前提とした支援」で、自立できるように支援をはかる引き出す支援でなければならない。災害救助法の自己解決主義は、自立を引き出そうとする配慮ゆえのもので、切り捨てることを意図していない。自立を促す対応とセットに災害の保護を考えないといけない。
救助項目としての住宅の修理は、救助法の制定時にはなかった。制定後3年目に住宅修理は追加されている。自力再建支援をはかる姿勢が、住宅修理支援につながった。全壊の被災者には与える支援で仮設住宅の提供をはかったが、それでは半壊の被災者は救えないことが明らかで、半壊の被災者には引き出す支援で修理をサポートし自力解決を促そうとしたのである。
◆災害救助法の改正に向けて(その3)・・教育を含めた包括的救助の仕組み
災害救助法から学ぶべきことに、生活保護を包括的に捉えた救助の総合的な体系があります。災害救助法の「救助の項目」を見ると、生活の場として避難所や仮設住宅などを確保することはいうまでなく、「衣食」さらに「医職」も救助の主要な項目として位置づけています。
医療の支援には、助産も含まれています。職業の支援については、「生業に必要な資金の給与また貸与をはかる」として、生業の確保が被災者の自立に欠かせないとの視点が貫かれています。現在は、住宅支援に比べて生業支援が疎かになる傾向があるだけに、これまた原点に回帰する必要を教えています。
中でも見逃してはならないのは、子どもたちの教育支援です。学用品等の現物支給という形で支援をはかることになっていますが、これは子どもの教育が救助や復興できわめて大切だという考え方を反映したものです。
現在の、学校の再開を後回しにしたり、学校の先生を子どもから取り上げ避難者のケアに駆り立てる傾向を見ると、子どもの教育を救助の最優先課題として位置づける災害救助法の原点を、再確認しなければなりません。
災害救助法で何よりも最初に改めるべきは、こうした原点を忘れた姿勢や誤った法の運用のあり方だといっても、過言ではありません。