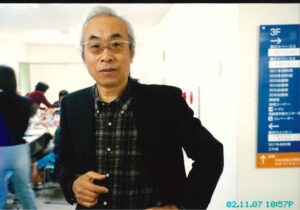この動画は、阪神・淡路大震災の追悼行事の模様をダイジェストで収めたものです。
1. 運営・準備の様子
会場での設営、ボランティアへの注意事項の共有、パンやコーヒーの提供に関する打ち合わせなど、イベント運営の裏側が記録されています。
2. 駒ヶ林中学校 1年生によるメッセージ
震災を知らない世代の中学生が、家族や地域から聞いた震災の教訓について述べています。
「私たちが安心して過ごしている毎日は決して当たり前ではありません」
「震災の教訓を忘れず、防災について一人一人が考え、日々の行動に生かしていくことが大切です」
メッセージの後、復興を願う歌「しあわせ運べるように」が合唱されました。
3. 学生ボランティアの言葉
神戸大学などの学生たちが、ボランティアに参加した感想や決意を語っています。
・神戸大学の学生: 春から教員になるにあたり、震災を知らない子供たちにどう教訓を伝えていくべきか、今日の経験を生かしたいと述べています。
・神戸親和大学の学生: 大阪出身で神戸での「1.17」の重みを初めて知り、将来教師として震災を風化させないようにしたいと語っています。
4. 黙祷 夕方の5時46分
時刻が5時46分(※動画内では夕方の5時46分に合わせて実施)になると告げられ、会場全体で犠牲者への黙祷が捧げられました。
5. 竹灯籠の様子
日が落ち、広場に並べられた竹灯籠に火が灯され、震災への思いを馳せる幻想的な会場の様子が映し出されています。