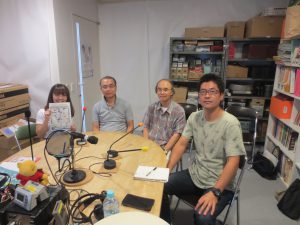今月のママトーーク!!!
第6回目のテーマは「理想の育休とは?」

出産予定日の6週間前から出産日の8週間後まで取得できる産休に続いて、出産日から1年間(こどもが満1歳の誕生日前日まで)取得できるのが育児休暇(=育休)です。ただしお給料は会社には支払い義務はなく、それぞれの判断に任されている現実。
せっかく休暇を取って育児に専念したいと思っているのに、会社から遠慮なく電話がかかってきたり… 休暇中の行動を会社の人に見つかると、「お給料もらってるくせに平日に遊びに行くなんて!」など非難の対象になるのでお出かけすら気をつかう!?とか… 赤ちゃんの1歳の誕生日が近づくと職場に戻らなきゃいけない!と、保活に必死になったり、苦渋の卒乳に親子で泣きながらトライしたり…
「さぁ 仕事のことは気にせずに思う存分 子育てしておいで〜〜」、「期間なんて気にせずに自分が仕事復帰したいと思うタイミングで帰っておいで〜〜」、というような思いやりのある温かい育休の整備は叶わないのでしょうか。
意見が一致しておもしろかったのは、「0歳児の育児なんて、辛いこと99%、楽しいこと1%」ということ。1歳から3歳にかけてどんどん可愛さや楽しさが増していくのに、その期間を他人に預けるなんてもったいない! 0歳児の育児が一番苦痛だった、というのが実感でした。
仕事がしたい人、もっと育児してたい人、個々の思いが叶うように!
選べる自由がありますように! と願います。