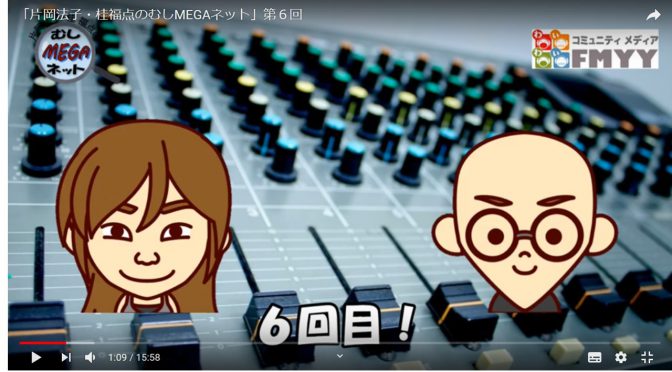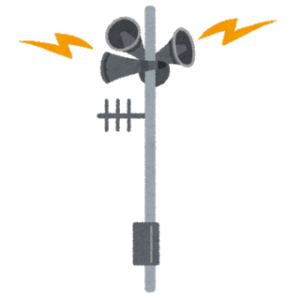今回は大阪市東淀川区にある
「おのころ食堂 淡路島」をご紹介します。
淡路島出身のマスターのこだわり、淡路産の食材をつかった数々のお料理。
そして、それだけでないご夫婦の・・・に、『むしMEGAサイズ』でせまります!
**お知らせ
来年2021年1月の放送は、第3週2021年1月16日、阪神・淡路大震災のメモリアルディの前日にお送りする予定です。
「暮らしを守る」タグアーカイブ
防災、被災地支援に関連した番組
2020年11月28日「らの会わぃわぃbyネットワーク長田」ゲストはM.Y.S.Kobe!
今日の進行は交友の幅広い石倉悦子さん。
今回はM.Y.S.Kobeの代表中村美智留さんをお連れくださり、『神戸に笑顔の種をまく』その取り組みをお話しいただきました。
いろんな取り組みの中から、神戸といえばFASHON!ということで、「ユニバーサルファッションショウ」について写真と共に詳しくお話しいただきました。
第1回は板宿商店街にレッドカーペットのRUNNWAYをつくり、そこで車いすの方々など応募されたモデルさんにそれぞれの特性を隠すのではなく、それを活かしたファッションで登場いただいたそうです。
第2回は須磨海岸で「須磨元気フェスティバル」のビーチマットをRUNWAYにしての開催したのだそうです。
以上2回も衣装提供は,FMYYでもおなじみのFREEHELPさんやホザナ・ハウスさんなどのチャリティショップさんです。**FMYYとのご縁にもびっくりです。
そして2021年5月開催予定の第3回は、今度はデザインも募集、子どもモデルも募集というさらにバージョンアップ!
会場は須磨寺さんでの実施だそうです。
この番組はプロジェクトMの提供でお送りしています。
(番組提供のプロジェクトMは、M.Y.S.Kobeへの支援もされています)
2020年11月21日第38回 『街ブラ~人と街とくらしを探る』
第38回 『街ブラ~人と街とくらしを探る』
今月の街ブラは、兵庫区にあります 国際交流シェアハウスやどかり オーナー中野みゆきさんをゲストにお迎えしました。
今から五年前の2015年7月にオープンした国際交流シェアハウスやどかりは、留学生や技能実習生など外国にルーツを持つ方々の日本語支援や生活支援のために設立されました。
開設当初はたった一人の受け入れから始まり、今では満室になるほどたくさんの外国人の方々が利用されるようになりました。
中野さんは、日本語教師として留学生と接するなかで、留学生が地域住民の方々と交流し、もっと地域とコミュニケーションがとれるような場所をつくりたいと考えたそうで、それがこの活動を始められたきっかけだそうです。
ところが、新型コロナの影響により、今年に入ってから留学生も技能実習生も受け入れができなくなり、一時は閉館も視野に入れていたそうです。
しかし、留学生をはじめ地域の方からも励まされ、クラウドファンディングに挑戦する事などによって、一番辛くて苦しい時を乗り越えられました。
これからも中野さんは、新型コロナの影響で苦しんでいる留学生をサポートするために活動を考えてらっしゃいます。
中野みゆきさんは、いつも前を向いている芯の強い素敵な女性だなと思いました。
是非、国際交流シェアハウスやどかりのFacebookやSNSをチェックしていただき、日本で頑張っている外国人の方々の様子をご覧ください。
国際交流シェアハウスやどかり
 は、日本に初めて暮らす留学生や技能実習生の方々が安心安全に暮らせる場所として、なくてはならないものだと強く感じました。
は、日本に初めて暮らす留学生や技能実習生の方々が安心安全に暮らせる場所として、なくてはならないものだと強く感じました。
これからも街ブラは、輝く人・街を応援します!
オープニング曲 『171』
エンディング曲 『Touch the rainbow』
演奏 BloomWorks