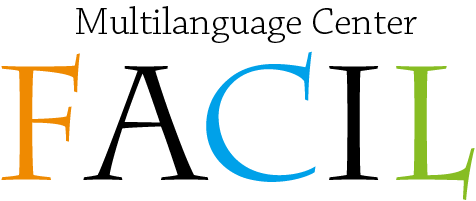1995年阪神淡路大震災で被災した神戸で
翻訳ボランティアを開始した私たちの活動
20年以上経った今でも言語バリアに悩む在住外国人は後を絶ちません。

阪神・淡路大震災の頃と比べると、その多言語対応はずいぶん改善されたと言えます。
小学校の就学案内、定額給付金のお知らせ、ごみのルールのことなど、多くの情報が数言語程度に翻訳されていることも、あまりめずらしくなくなってきました。
それでも、市区町村役所の窓口、医療機関、小・中学校の教育現場などではまだまだ言葉のバリアによって意思疎通がうまくとれない場合がたくさんあります(FACILでは特に医療通訳への取り組みをしています「医療通訳システム構築事業」を参照)。この意思疎通がとれないという現状を、外国出身の住民自身の自助努力による日本語の習得ということだけで解決するという考え方でいいのでしょうか?
コミュニケーションのためのふたつの道筋
『日本語を習得する必要性』と『自分の母語で情報を得る権利』

まだ日本語の理解の不十分な住民にとって、日本社会で暮らすことはハンディを伴うものです。日本で生活をするために日本語は、コミュニケーションの道具としてもちろん習得することが必要です。
しかし、情報を得たり、コミュニケーションをとるための、その社会で使われている言葉が大切であるとともに、生まれ育ってから使ってきた母語も、それによって思考が組み立てられ、自分を一番表現できる大切な言葉でもあります。自分の母語で話すことによって、安心感を得てストレス解消にもなる場合があります。
母語以外の習得には誰でも時間がかかります。さまざまな背景や目的があって日本で暮らしている多くの人たちは、日本語を十分習得してから日本に来ているわけではないでしょう。この人たちが日本語を習得するまでの間、大切な情報を伝えるためには、できるだけ多くの言語にして伝えていくのは、受け入れた社会の責任でもあります。
さまざまな背景で地球上の多くの人が移動をして暮らすグローバルな社会において、どのような環境であっても人間らしく暮らすためには、その社会で使われている言葉を習得することは、義務でもあり権利であると言えます。そしてまた、自分の言葉で情報を得たり表現をすることも、同様なのではないでしょうか?
言葉において、このふたつの道筋を考えられている社会は、とても民主的で成熟した社会で、すべての住民にとって暮らしやすい豊かな社会にちがいありません。
翻訳を活用した双方向のコミュニケーションの先

では、そのような道筋が考えられている社会がどうして豊かな社会なのか、私たちの活動の経験からお伝えします。
阪神・淡路大震災時は、日本語がわかる被災者でも情報が届かずに大変不安な思いをしましたから、日本語の理解が不十分な住民の不安はかなり大きかったと想像できます。
神戸市長田区には多くのベトナム人が住んでいますが、彼らの多くは「避難所」という難しい日本語を知りませんでしたが、地震が起きて多くの負傷者が出たので、みんなと一緒になってけが人を病院に運び、避難所では残っていたお肉でバーベキューをしてみんなを元気づけました。
震災時は、隣に住んでいる人と顔見知りだったかどうかが生死を分けました。
日常的に挨拶もせず孤立して暮らしていると、ガレキの下敷きになっていても見つけてもらえないからです。
隣に住んでいる人がもし中国人だったら、日常的に情報を伝えてコミュニケーションをとれていたら、私たちを助けてくれる隣人となるでしょう。
情報は、伝えるだけの一方通行ではなく、コミュニケーションをとるということは、受け取った人からもまた新しい情報が返ってくるという双方向のものであるはずです。
日本社会では常識と考えられていることが、別の国の文化背景を持つ人たちからは非常識なことであったり、その逆もあると思います。
日本のことしかしらない多くの住民にとって、外国出身の住民の視点で見えることを知ることができれば、今まで気づかなかったことに出会えるかもしれません。
その結果、自分にとってよりよい環境がつくれるかもしれないし、日本の良さを実感することもあるでしょう。
翻訳通訳事業を通じて私たちがをめざすもの

私たちが活動をしている地域は、たくさんの外国出身者が住んでいます。
震災前から、地域の夏祭りといえば、たこ焼きや焼きそばの屋台が出て、盆踊りを楽しんでいましたが、震災を経験して外国出身者であろうと日本人であろうと同じ被災者になって大変な避難所暮らしを経験したことから、せっかく同じ「まち」に住んでいるのだから、ベトナムの生春巻きやネパールのカレーや韓国のチヂミやペルーの焼き鳥の屋台も出してほしいと声をかけて、今では夏祭りに自然に多国籍な料理が並ぶようになり、みんなもそれを楽しみにしています。
ひとりひとりがコミュニケーションをとるための少しずつの努力をしたその先には、このように多様で豊かな自分の「まち」が待っているのです。そのプロセスは簡単ではないし、
ケンカをしたりもめたりもしながらですが、震災から20年経って、私たちはそれが必ずできるという実感をもって、多言語センターFACILのさまざまな事業に取り組んでいます。